今回は森保ジャパン2戦目となるキリンチャレンジカップ2018パナマ戦の課題について検証していきます。
またしてもスコア3-0で快勝という形でしたが、実際試合ではどういう事が起こっていたのかを試合を見直して課題を見つけ出していきます。
INDEX
パナマ戦における有識者の課題
今回もカトルセ・スカサカ・Leo the footballの試合どうだったかを見ました。
スカサカ岩政さん・市川さん・永井さん・清水さん
⇒おそらくウルグアイ戦でもやらない⇒アジアカップまで試すタイミングがないのではないか
⇒だったら狭い場所でプレーできる堂安・中島の方が良い
- ボランチのアンカー落ちの弱点である、大迫・南野の場所で取られた時の中盤の薄さがピンチを招きかねないのでそれを想定した守備練習をしておくべき→☆1
- 1stラインで取れなくて、少し運ばれてからの組織的守備が少ししんどかった⇒☆2
カトルセ戸田さん・中西さん
空走りで相手のラインを下げる動きが重要⇒4
1stラインディフェンスが良い⇒5
三竿の位置がマズイ⇒6
LEO the footballさん
日本とパナマの攻守のフォーメーションについて
お互いのフォーメーションは以下の形が基本でした。
- 日本(攻)→パナマ(守)
- 日本(守)←パナマ(攻)
日本が4-2-3-1の攻撃に対してパナマは4-4-2で守備、パナマが攻撃の際にはお互い4-4-2でした。
Leo the footballさんがわかりやすく解説していたのですが、日本の攻撃はさらにここから以下の3つのビルドアップの形(サリダデバロンによる相手の1stライン突破手法)を作っていました。
パターンA

コスタリカ戦でも見せていた青山か三竿がCBの間に行くいわゆるアンカー落ちです。これによって相手FW2枚に対して3バックが数的優位となり、富安の前に運ぶドリブルによって1stディフェンスラインを突破します。
最も多く見せていた形で、富安から大迫・南野・伊藤に良い縦パスが何本か出ていました。
ポイントは両サイドバックが相手のWGとSBの間に位置することでどちらにマークさせるか混乱させる、いわゆる中間ポジションをとることです。これによって伊藤や原口のマーカーも混乱させ、結果以下のような2対1を作り出す狙いがあります。

2対1を一旦外側でつくり、1を無力化させて、カバーに来た相手と今度は2対1をつくるというようにどんどん2対1をずらして外から内へと2対1状況を進行させるというのがサッカーの崩しの基本ですね。
パターンB

青山か三竿がCBの外側に行く、サイドバック落ちによる3バック構築です。
あまり多く見られなかったですが、パターンとして持っておきたかったのか、もしくは槙野がパスが得意じゃないから作ったパターンなのかどちらかかなと思いました。
パターンC

佐々木がCBに吸収され、室谷を大きく前に張り出させたフォーメーションです。
原口の前に広大なスペースを作り出すこと、伊藤・室谷で2対1を作り出すことが目的としてあるのだと思います。これができるのがCBもできる佐々木の良い点でしょう。
試合を見返して実際どうだったか
✩1ボランチのアンカー落ちの弱点を意識した守備について
青山がアンカー落ちして、大迫にボールが通ったものの、ボールを失った場合を想定します。
以下の図のように佐々木が攻撃的すぎるポジションを取っている場合、7番の前に広大なスペースがありますので、7をケアしたポジションを取るというのが1つ考えられます。

さらに重要な点が攻守の切り替わりに対してボールを失った危機感を感じ、南野が素早くボールホルダーの20番に寄せ、取り返すもしくは遅らせる事が重要です。
三竿は7と佐々木、富安と8の位置関係を確認し、どこでもカバーにいけるように首を振ったりポジション修正をする必要があると思いました。
✩21stラインでのディフェンスで取り切れなかった場合の守備
これはロシアワールドカップからの課題ですが、個の強さや上手さで日本の1stラインディフェンスが突破されると途端に取りどころがなくなってしまいます。
今回のパナマ戦でも、崩される事はなかったですが、何度かずるずると取れないまま前進を許すという事が相手のチャンスにつながっています。
正直これに関しては解決策が何なのかわかりませんが、2ndライン、最終ラインでのディフェンスは今も昔も課題であり、1stラインでのディフェンスは日本の強みであるとこの試合を見ても感じました。
✩3両SBが中間ポジションを取る日本の理想の攻撃
戸田さんが言う日本の理想の攻めの1つを紹介します。
- 1
- 2
- 3
槙野が持ち上がり→原口に縦パス→佐々木に落とし→南野へ斜めパス(スルー)→大迫へ
という流れです。大迫はオフサイドでしたが、パナマの2ndラインを突破できていました。
佐々木についていたマーカーだけ見ると、最初は相手のWGがマーカーでしたが、原口の落としを受けた段階で、自分の元マーカー(WG)と原口のマーカー(SB)と南野のマーカー(DMF)の3名を中ぶらりんの状況にしています。
ここから脱出できたら一気にチャンスとなる状況で、見事に相手の間を抜くパスで大迫へとボールを届けました。
中間ポジションで相手2枚以上を無力化させる事に成功していて良かったと思いました。
✩4空走りで相手のラインを下げる動き
戸田さんの解説内であった26分での選択についてです。
- 1
- 2
- 3
原口の外をまわる南野へパス→縦にスプリントする原口→南野から原口へ縦パス
という流れでした。原口がボールのない部分での縦スプリントによって相手DFを大きく下げさせています。
すると以下に新たなスペースができます。

原口にパスを出さずにこのスペースを伊藤が使えたら良かったなというお話ですが、これは結果論的なところもありますね。
ただ、原口の良さはこのスプリントをしてくれる所ですので、それを理解して誰かがこのスペースに走りこめるようになってくればより日本は強くなるだろうなと感じました。
※カトルセではボールが来なくてもスプリントすることで相手のフォーメーションをバラバラにすることを『空走り』と表現されていました。
✩5 1stラインディフェンスが良い
これは今回だけでなく、ずっと日本の強みであり、心臓にあたる部分です。良かったシーンを紹介します。
- 1
- 2
- 3
- 4
➀大迫がゆっくりとボランチへのコースを切りながら寄っていく
②CBは仕方なくSBへパスを出す。この時CBが蹴るモーションに入った段階で伊藤がSBに向かってスプリントをかける
③伊藤が縦パスを切りながらSBへ寄せる。中向きにさせる
④伊藤のスライディングでボールを大迫の方へかき出す
という流れでした。伊藤の寄せと、それに連動した大迫・青山・南野の動きが素晴らしいですね。
写真2→写真3に移る間に、大迫はボランチのマークを青山に渡し、CBへ向かっています。
南野はもう1枚のCBへのパスコースを狙っていますので、伊藤とマッチアップしたSBはかなり選択肢を限定されていて、結局ボールを失ってしまいました。
続いて31分頃のシーンです。
- 1
- 2
- 3
南野がCBへ寄せる(中を原口・三竿が、逆CBを大迫が切る)
→SBへパスが出ると原口がスプリント
→原口のスプリントに連動して佐々木が縦を切る、三竿が中を切る
という流れでした。これは結局ボールを取れなかったのですが、原口がボールカットできそうなおしいシーンでした。
この2つのシーンだけ見ても、日本の前からの守備はかなり相手を困らせています。日本の強みですので、前線の選手の誰が出てもこれができるようになって欲しいなと思います。
※ロシアW杯の時だと宇佐美がこれをできなかったので、かなり痛かった。。
✩6 三竿の位置がマズイ
戸田さんのダブルボランチのポジショニングについてのコメントです。
- 1
- 2
- 3
右OMFがボール保持しているので、原口がWGへのパスコースを切りながら南野とはさみに行く→SBへパスを出し、1-2で右OMFが抜けだす
という流れです。
次の図を見てみましょう。

三竿はこの黄色のエリアにいるべきだという戸田さんのコメントですが、確かにその通りだと思いました。
相手WGも気になりますし、青山は最終ラインに入っているので、いつものダブルボランチの感覚でなく、1ボランチでの人への付き方が重要だったシーンだなと思いました。
ボランチは守備でのカバーリングが重要ですので、対人の強さだけでなく、チームのバランスを見たポジショニングができて初めて「三竿は守備ができる」というキャラクターになると思います。
同じようにW杯の時の山口蛍選手も対人が強いので守備ができるというイメージがありましたが、ポジショニングがよくないので、実質守備ができていない印象でした。
まとめ
コスタリカ戦での課題を検証して、僕が確認できた日本の課題は以下でした。
- ビルドアップで狙う形に合ったWG選手起用(スペースに走りたい選手と狭い所で受けられる選手)
- 2nd・最終ラインでのディフェンスの強化
- 三竿のポジショニング能力の強化(カバーリングとボールを引き出す動き)
- CBの運ぶドリブルのスピードと精度と勇気
ビルドアップは比較的うまくできているので、自分から最も近い選択肢ではなく1つ奥が見られるように意識することでさらにシュートまでつながる攻撃が増えると感じました。
また、今回とは別でビルドアップ時にCBと同数のプレッシングをかけられた時にどう対処できるかもまだ見られていないので、気になります。
守備ではボランチのカバーリングと2nd・最終ラインをどう強化できるかが今後の課題ですね。
最近の数試合で海外組だけでなく、皆が1stラインでのディフェンスを習得するとかなり相手を困らせる事ができる事を実感します。
次のウルグアイ戦も初めての強豪との試合ですので、どんどん課題を見つけて修正して強くなっていく姿を見たいですね!

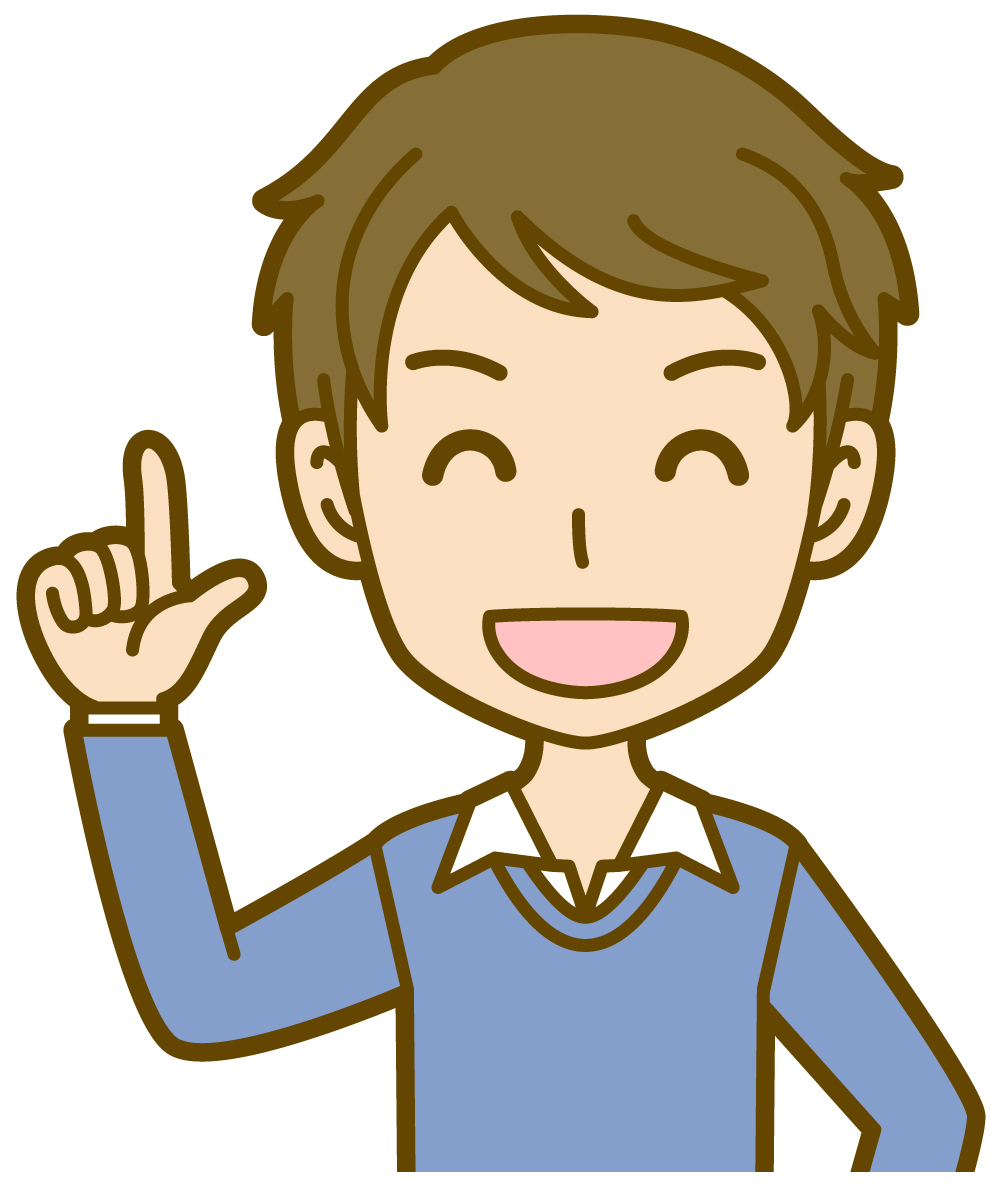
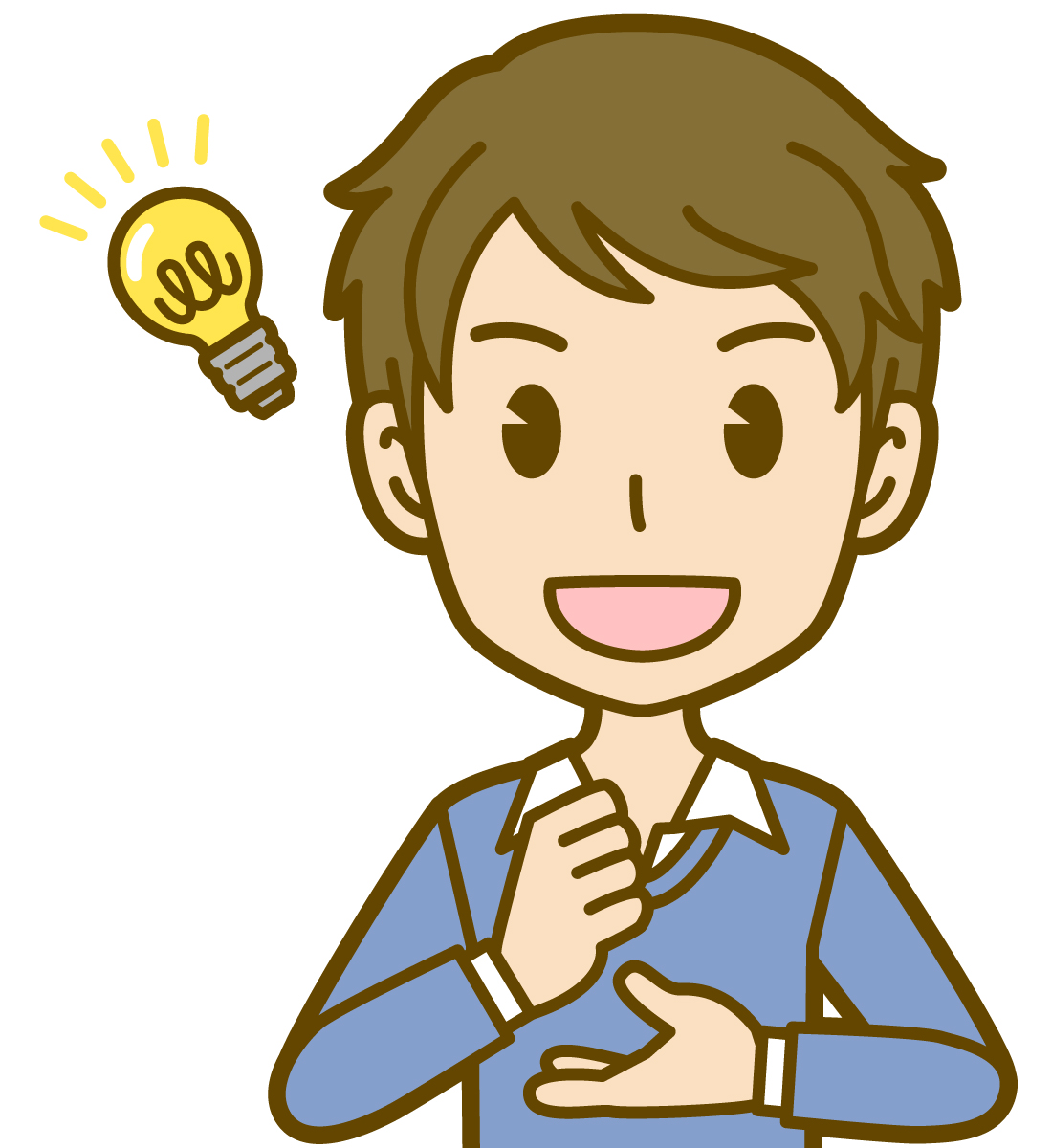





























コメント
はじめまして。すごい分析力ですね。懐かしい映像を見つけましたよ。小野伸二、高原、小笠原、クラウチ、アンディジョンソンが出場している試合です。1999年に開催されたワールドユースの試合です。
ふっと様
はじめまして。コメントありがとうございます!分析というよりエラい人のコメントを聞いて、実際の試合でそんなシーンがあるかどうかを見ていった感じですが、ふっと様の学びにつながったのなら良かったです!ワールドユースの試合映像なんて見た事なかったです!各個人のスキルは今でも十分通用するレベルですね!やっぱり昔はライン間が広いので、2列目の攻撃選手に時間が与えられることで、FWがスルーパスを裏抜けでもらってシュートを打つスポーツという感じが今とは少し違いますね!情報ありがとうございます!